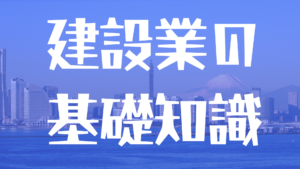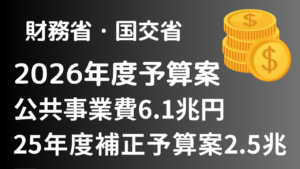「住宅設計」の仕事内容とやりがい、向いている人のポイントについて【建設業の仕事】
住宅設計は建築学生の志望職種のなかでも、最も人気が高い仕事のひとつです。「住まいを通じてお客様の人生に深く関わることができる」点に魅力を感じる人が多く、また、建築を学ぶきっかけとして、「家族が新居を建てる際に担当者の方の親身な対応に感動した」など思い出を語る人や、大学での建築学習や地域の住宅見学会を通じて、「住む人のライフスタイルや価値観がそれぞれ異なることを学び、理想の住まいを形にすることにやりがいを感じた」という人も多いものです。
それだけ「住まい」という建築物は、人の生活に欠かすことができない、とても身近で大切なものだといえるでしょう。
本記事では、ハウスメーカーの実例を中心に、住宅設計の具体的な仕事内容や、やりがい、魅力について解説していきます。
どんな人が住宅設計に向いているのか、適性を見きわめるポイントも紹介していきますのでご一読ください。
住宅業界にはどのような業態があるのか?
住宅業界とは、おもに個人向けの一戸建て住宅を扱う業界です。注文住宅や分譲住宅、賃貸住宅の設計や建設、販売を手掛けています。住宅業界に属する企業の種類は主に以下のとおりです。
・ハウスメーカー
・工務店(地域ビルダー)
・パワービルダー
・設計事務所
それぞれの特徴を要約して紹介していきましょう。
■ハウスメーカーの特徴
ハウスメーカーは、全国で事業展開している住宅建設会社であり、自社工場による建材の大量生産と統一規格の採用により、注文住宅の量産が可能です。
有名人を起用したテレビCMや広告などにより広く認知されており、モデルハウスや展示場も各地に設置されています。また、効率的な工程管理により短期間で住宅を建築できることも特徴です。
一方、意匠や間取りの選択肢が限られている、他の業態と比較して割高となる傾向がある点も指摘されています。近年はデザイン性や耐震性能、環境性能の向上にも取り組んでいて、大企業ならではの強い商品開発力を発揮しています。
■工務店(地域ビルダー)の特徴
工務店は地域密着型の住宅建設会社です。ハウスメーカーより規模は小さいですが、商圏とする地域では施工実績が豊富です。一般的な木造軸組み構法を採用して、間取りやデザイン、素材などの自由度が高く、施主の希望に合わせたオーダーメイドの家づくりをしている企業も多いです。
広告宣伝費や人件費が少ない分、コストを抑えやすいことやアフターフォローが丁寧なことも特徴です。
地の利を活かして安く土地を仕入れることで、地域ビルダーとして展開している企業もあります。
■パワービルダーの特徴
パワービルダーは、初めての住宅購入者向けに土地付き一戸建て(床面積30坪程度、2,000~4,000万円)を年間1000戸以上販売する建売業者を指します。
パワービルダーという呼称は2000年頃から使われ始め、首都圏では大手5社のシェアが急増しました。地域展開から全国展開へ規模を拡大した企業もあり、現在では「強い勢いのあるビルダー」という意味でも使われています。
建材・設備の共同仕入れやプレカット工場の運営にも力を入れています。
■設計事務所の家づくりの特徴
設計事務所は設計図書の作成に特化して、施工部門を持たないのが特徴といえます。施主と相談しながら、家族やライフスタイルに合わせた、完全オーダーメイドの住宅を設計し、工務店などに施工を委託して、工事監理を担当します。
納得のいくオリジナル設計の住宅が完成しますが、完成までの時間は長くかかる傾向があります。唯一無二のこだわりが感じられる住まいを特徴とします。
住宅設計職について
住宅設計職は、ハウスメーカー、工務店、設計事務所など、業態ごとにお客様への提案方法が異なります。
たとえば、工務店や設計事務所では、お客様の要望を聞き取り、それらを可能な限り実現できるよう構造や設備、仕様などを計画します。一方、ハウスメーカーでは、自社の工法や構造規格の範囲内で、商品化された住宅から、お客様の要望に合うものを選んで提案し、必要に応じて調整を加えて設計を進めていきます。
ハウスメーカーにおける住宅設計職の仕事内容
住宅設計では、敷地条件を把握し、間取りや広さ、日当たり、設備、収納などを計画して提案します。住宅設計職は、自社の構造や工法を活かしつつ、技術的に可能な範囲でお客様の希望に合わせた設計プランを提案し高品質な住宅を提供します。
打合せによるプランニングや提案だけでなく、住宅建築に必要な他の業務も担当します。
この記事では、設計職の主な仕事の流れと内容について説明します。
■住宅設計職の仕事の流れとその内容
1.営業設計・企画設計
担当営業と一緒にお客様と面談し、要望を確認しながら企画を立てていきます。ラフ図面やパースなどの資料でイメージを共有し、打合せを重ねてニーズをすり合わせます。
初めて自宅を建築するお客様にも、わかりやすく説得力のある提案をして信頼を得ることが重要です。また、設計案やパースなどをわかりやすく作成するためにCADやCGソフトを扱うスキルが必要となります。
2.実施設計
住宅の間取りなどが決定後、構造や内装材、設備などを検討し、方針が決まれば建築基準法等も確認します。ハウスメーカーでは自社規格に合わせた商材から選んで提案するシステムになっている会社もあります。施工性を考えて、寸法や材料、構造、設備など詳細な設計図書を作成して提示していきます。
3.見積書の作成
実施設計をもとに、工事を行うために必要な金額を積算して見積書として提示します。工事内容や工程について説得力のある説明を行うことも大切です。
4.契約締結・各種発注
契約を締結して、住宅建築に必要な資材および設備の発注を行います。図面に基づき必要部材を選定し、工期に合わせて手配します。これらの業務は工事を予定通り進める上で重要です。建築士は建築確認申請を行い、工事開始に備えます。
5.工事着工・監理
実施設計図をもとに、施工部門に工事内容の引継ぎをします。工事中は設計図書通りに工事が進んでいるか確認する監理業務を行い、工事完了後には設計変更などを反映した竣工図を作成します。
住宅設計職の実際の業務範囲はハウスメーカーによって大きく異なります。
住宅設計職がどこまでを担当しているのか、企業との面談や、OB・OG訪問で確認することで、具体的な仕事内容をつかみやすくなります。
経験者が語る「住宅設計職の魅力とやりがい」
1.顧客の夢を形にする喜び
住宅購入は、お客様の生涯で一度しかないと言われる重要イベント。それをサポートして、ライフスタイルや価値観を丁寧にヒアリングし、住まいという形にしていくプロセスは、まさに共感と創造の融合。お客様やその家族が完成した家を見て喜ぶ姿に、設計者は深いやりがいを感じるのです。
プロとして、お客様が考えるよりも、もっと良い提案をすること。それが住宅設計職の醍醐味です。
2.自分の作品が街に残る誇り
設計した住宅は年月とともに地域に根付き、人々の生活を支えます。建物が街の一部となり、個人の空間でありながら周囲の景観にも影響していきます。
設計職は社会環境の向上に貢献でき、評判によって近隣から新たな注文が入ることも多いものです。
3.毎回、新しい挑戦ができる
ハウスメーカーの住宅は規格化されているものの、お客様の要望や家族構成、土地や周辺環境は毎回異なります。設計はお客様・営業・設計者・自然環境が共同で作り上げるため、物件ごとに新たな発見があります。
設計者にとっては、毎回初心に戻って取り組むことで刺激や達成感を得られのです。
4.チームでつくる達成感
住宅は設計職だけでなく、施工業者と協力して完成します。他の建築物より工期は短めですが、複数の物件を同時に進めることも多いのです。工程ごとに着実に仕事が進み、竣工や引渡し時には、チームに大きな達成感をもたらします。
ハウスメーカーの住宅設計職に向いている人
住宅設計職は、常に新しい知識や技術を学ぶ意欲が必要です。また、お客様や多くの専門業者と直接関わるため、対人スキルやコミュニケーション能力も重要です。
以下は、「住宅設計職に向いている人の特徴」になります。
1.社交性がある人
お客様との打ち合わせが多く、信頼関係を築くことが大切。人と話すのが好きで、さまざまなタイプの人と柔軟に接して、要望を引き出すことができる人が向いています。
2.奉仕の心を持っている人
交渉の主役はお客様。「お客様のために」考え、「喜んでいただくための」提案に徹することができれば、ライバル会社の設計職に勝つことができます。
予算やデザインなども、お客様の意見・要望を超える「もっと良い」提案ができることが強みとなります。
3.家づくり、図面作成が好きなこと
間取りプランや図面作成など、毎日飽きずに楽しめること。膨大な繰り返しをしていきますので、何度でも設計できるくらい、根っから好きな人が、やはり一番向いています。
4.プレッシャーに強い人
契約して終わり、設計図書が完成したら終わりという仕事ではなく、その後の仕事が責任重大です。
納期管理や予算管理、クレーム対応なども必要になり、お客様にとっては一生で一番高い買い物になるだけに、責任感やプレッシャーに強いことも重要です。
5.計画的に物事を進められる人
住宅設計職は、進行中の物件を複数担当することが多く、物件によって進捗や必要な手配もそれぞれ異なります。
営業職と連携して、至急でプレゼン準備を進めなければならないことも多く発生するため、マルチタスク管理に強い人が向いています。
6.キャリアアップを意識できる人
大手ハウスメーカーでは、経験を積んで、建築士資格を早期取得するなど、段階的にスキル、実力を伸ばしていくことで、住宅設計部門のマネジメントや教育指導に関わる道が開けてきます。
キャリアアップやステップアップを意識して成長していける人には適職となることでしょう。
ハウスメーカーの住宅設計職に向いていない人
1.コミュニケーションにストレスを感じる人
住宅設計職は、お客様や営業職、施工チームとの交渉が多いため、対話や調整が苦手だと業務が負担に感じやすい面があります。また言葉だけではなく、相手の顔色や態度などを通して、求められている要望を読んでいく必要があるため、感情をキャッチすることが苦手な人はストレスを感じるかもしれません。
2.スケジュール管理が苦手な人
担当案件の工程や進行中プロジェクトに合わせて、打ち合せが多く行われ、準備や納期が厳しくなっていきます。
時間に追われるのが苦手な人や、つい忘れてしまう人、先手管理をイメージするのが苦手な人は、苦労する可能性があります。
3.学ぶことを苦痛に感じる人
住宅設計職は、新商品や仕様変更、建築技術やデザインの変化など、常に知識や情報をアップデートしていく必要があります。
近年は建築材料の価格や納期も変動が激しく、多くの情報を学びなおしていく必要があります。
さらに設計職として熟知していなければならないのは、建築基準法などの法規制です。法改正にも対応が必要となりますので、学び続けていく必要があります。
4.細かな作業や集中が苦手な人
設計図書の修正や、スケジュール調整など緻密な取組みが必要です。ミスを防ぐには、細部に注意する集中力や、時間が掛かってもへこたれない忍耐力が必要な場合があります。
住宅設計を目指すうえで重要な企業研究のポイント
ハウスメーカーによって「注文住宅」「分譲住宅」「賃貸住宅」といった、扱う住宅の種類や、自由設計型・規格型など提案方法が異なり、それによって住宅設計職の仕事も変わります。
自分がどのように住宅提案したいかイメージすることで志望動機が明確になります。企業ごとに力を入れている住宅領域は異なるため、企業研究ではここに注目してみましょう。
■注文住宅
注文住宅の設計には、自由度の高いフルオーダー住宅と、仕様がある程度決まっているセミオーダー住宅があります。フルオーダーは間取りや設備をすべて自由に選べますが、セミオーダーは基本仕様の範囲内で選択します。
どこまで設計に関わるかは、企業の主力商品や用意されているオーダータイプによって異なります。
■分譲住宅
分譲住宅は、企業がまとめて土地を購入し、区画ごとに住宅を建てて販売するものです。敷地の形状や日当たり、風通しなどを考慮して計画し、統一感のあるデザイン・仕様で住宅街を作ります。
工務店やパワービルダーは、街中の空き地を分割して、数棟の安価な建売住宅として販売することが多く、大手ハウスメーカーでは、郊外にデベロッパーが開発した広大な住宅分譲地で分譲住宅を販売するケースが多くなります。
■賃貸住宅
賃貸住宅は戸建住宅とは違い、住み替えが多いため設計提案の相手はオーナーです。各住戸の間取りや設備だけでなく、共用空間や仕上げ材も提案します。魅力的な賃貸住宅は需要が高まり、多くの人が住みやすくなります。
土地活用を目的に店舗併用住宅や福祉施設を展開する会社もあります。
ハウスメーカーは、それぞれ独自の工法や構造を持っています。住宅の構造は「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」の3つがあり、工法も様々です。各社の工法は、間取りの自由度や耐久性、耐震性、耐火性、工期、コストなどに違いがあります。
■木造
1.在来軸組み工法
柱と梁で建物を支える、日本の伝統的な工法です。
2.枠組壁工法(2×4工法)
規格木材でつくられた枠組みと壁・床・屋根などに構造用合板を打ち付けて、建物全体を箱状の構造で荷重を支える工法です。
3.木質パネル工法
工場で生産した床や壁パネルを現場で組み立てるプレハブ方式です。
■鉄骨造(S造)
建物の骨組み(柱や梁など)に鉄骨を使用する構造や工法のことです。
1.軽量鉄骨造
厚さ6mm未満の鋼材を使い、主に2階建て以下の住宅やアパートに用います。
2.重量鉄骨造
厚さ6mm以上の鋼材を使い、主に3階建て以上の住宅などに使われています。
■鉄筋コンクリート造(RC)
鉄筋を組んだ型枠にコンクリートを流し込んで建物をつくります。柱と梁で支えるラーメン構造と壁で支える壁工法があります。
まとめ
ハウスメーカーの住宅設計職は、安全で快適な住まいをお客様に提案する仕事です。
就活では企業ごとの特徴や設計者としてできる提案内容を比較し、将来の仕事として思い描いてみることで、自分に合った企業かどうかをイメージしながら進めることが重要です。
わが国の新設住宅着工戸数は、少子化の影響で今後は先細りしていく予測となっていますが、住宅設計職がなくなることはありません。但し、中小住宅企業の倒産は現実に増えていますし、大手ハウスメーカーでは戸建て住宅の販売戦略を海外に向けて進めることで実績を伸ばしています。
一方、国内では住宅建設で培った技術を発展させて、福祉施設や公共施設などの建築実績を伸ばしたり、大和ハウス工業や積水ハウスのように、総合建設業を傘下に加えて、高層マンションや商業施設、倉庫や物流拠点の建築など多角化を進めることで、大手ゼネコンを大きく超える売上実績を計上している企業もあります。
これらのことから、各企業の中期計画などを確認して経営方針を見定めることや、人材の採用、育成計画は、直近の実態を把握していくことも重要であると思います。
総合資格ナビでは本記事を読んで「住宅設計で活躍したい」と感じた皆さんへ、今後も業界・企業の情報提供を通じて応援していきます。
(本記事は、総合資格naviライター kouju64が構成しました。)